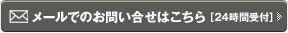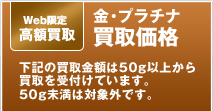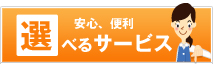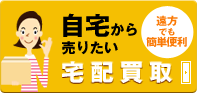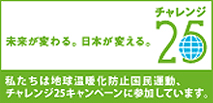スタッフ日記&お知らせ
2015-12-14 【諫早市・大村市・島原市の皆様 平和館諫早本店です】ギフト券♪金券♪販売・買取
諫早・大村・島原半島にお住まいの皆様
こんにちは( ´艸`)
平和館諫早本店のスタッフNです
いつも閲覧ありがとうございます
本日の諫早市は晴天です
暖かい陽気ですヘ(゚∀゚*)ノ
本日、お客様より航空券の株主優待券について
お問い合わせ頂きました
ANA・JALともに在庫がございます
有効期限等ございますのでお気軽にお問い合わせください(°∀°)b
尚、変動により買取金額や販売価格が不規則にかわります。
枚数に限りがございますのでお早めに
毎日お客様にご好評頂いております
JR特急券 長崎⇔福岡間も販売中です(・∀・)
席の指定等には対応しておりませんので
ご不明な点はスタッフまでお尋ねください
JR特急乗車券 一枚・2520円にて販売中です
ご不用になったJR券の(長崎⇔福岡 特急乗車券)も買取しております(^∇^)
有効期限によって買取金額が変わりますのでご注意ください。
その他、JCBギフト券・全国百貨店・ビール券・QUOカード・図書カード・・・
額面よりもお得にご購入頂けます
先日,JCBギフト券20万円分ご購入頂きました(^-^)/
お客様にお話しを伺ったところ
「車検の費用に利用する」との事でした。
目から鱗のご利用術Σ(・ω・ノ)ノ
いつも勉強になります
皆様も是非、便利にご利用くださいね
ギフト券の利用方法・使える店舗・用途など
ご不明な点はお気軽にスタッフまでお尋ねください(・ω・)/
平和館諫早本店
諫早市永昌町45番4号
0957-47-9714
午前10時~午後6時 年中無休
2015-12-09 休業のお知らせ!
12/18(金)社員研修の為 諫早本店休業させて頂きます。
ご連絡は小浜店へお願い致します。
0957-74-2003(営業時間) 9:00~19:00
2015-11-04 【スタッフ豆知識】 高級イメージのお酒、ブランデーの保存方法
ブランデーと聞くと、お酒に詳しくない人でも、「高級である」とか「高価である」というイメージが先に立つのではないでしょうか。勿論安価なブランデーも存在することはするのですが、高いモノが多いのは事実です。しかし具体的にどういうお酒かと言われると、説明出来る人は案外少ないと思います。
元々ブランデーは、フランス語で「焼いたワイン」を意味するヴァン・ブリュレから、オランダ語、英語を経てブランディワインとなり、そこから更にワインが取れてブランデーと呼ばれるようになったと言われています。
焼いたワインとは、つまり「ワインを蒸留したモノ」という意味で、ブランデーは基本的には葡萄から出来たワインを更に原料としたお酒ということになります
(ワインからではなく、ワイン醸造の際の搾りかすから醸造するブランデーや、他の果物から作ったブランデーも存在していますので、限定されるわけではありませんが)。
ブランデーの特徴としては、説明したように、蒸留酒であってしかもその後熟成しますので、アルコール度数がかなり高いということがあります。40度から50度前後の度数が一般的です。お酒としては間違いなく、酔いやすい部類にランクインするものです。
しかし、アルコール度数が高いお酒ということは、保存方法はそれなりに楽だということにもなります。アルコールで殺菌されますので、雑菌による腐敗が進まないからです。
ですので、保存方法としては、まずは高温多湿、直射日光などを避けるという、通常の食品の保存と同様の条件を守れば、「大きな」劣化は避けられるわけです。
勿論、アルコール度数が下がれば、菌が繁殖するようになって痛む可能性がありますから、栓のコルク等が劣化していないかチェックしてください。
また、保存方法が適切であっても、残念ながら一定量は蒸発してしまいますから、長期保存した場合には結構減ってしまう場合があります。
これは避けられませんので、諦めるしかありません。また香りの成分もどうしても抜けていくわけですから、この点も見逃せません。ただ、いずれにしても飲めなくなるという事態は通常考えられません。
さて、ではブランデーはワインなどのように、長期保存した場合に、味が深まったりすることはあるのでしょうか。これはワインとブランデーが樽から瓶詰めされる場合の差を認識しておく必要があります。
ワインの中には、樽から取り出して瓶詰めした後でも、熟成が進んでいるタイプのモノが存在します。これはワインの酵母がそのまま瓶にワインと共に入っている場合です。
これにより、保存している間に味に深みが出るという利点もありますが、逆に保存方法が非常に難しいということにもつながります。ワインセラーなどが重宝されるのもこのためです。勿論酵母が入っていないようなワインもあります。
一方、ブランデーは樽から出した後は熟成されることはありません。
ですから、長期保存しておけば味に深みが出てくるというわけでもありませんし、逆に過度の温度管理など、難しい保存方法も必要がないわけです。
そう考えると、量が減ったり、香りが抜けたりする可能性を考慮すれば、基本的にブランデーを長期間保存することによるメリットはないということになります。
結局のところ、ブランデーの保存方法はそれほど難しくはないが、出来れば早めに飲む方が望ましいという結論になります。勿論、開封してしまえば、酸化が一気に進みますし、劣化度合いが強くなることは言うまでもありませんので、ご注意ください。
0000-00-00 【スタッフ豆知識】 ウイスキーというお酒の良質な保存方法
皆さんが意外に気づかないポイントですが、実はウイスキーというお酒には賞味期限の記載義務はなく実質賞味期限というものは存在しません。
モルトウイスキーでもシングルモルトウイスキーでもブレンデッドでも関係なく、封を開けていなければ賞味期限は無い物と考えて大丈夫です。
保管状態が劣悪でなければ、ウイスキーやワインなどのアルコール度数が高いお酒は、中身が安定して品質を保てるため、食品表示法で賞味期限の表示が義務化されていません。
ここで雑学ですがビールに関しては、自主規制によって賞味期限が表示さています
ウイスキーというはお酒つまりアルコールですから室温で揮発します。
室温が高い場合、コルクをしっかりしめていてもウイスキーが劣化してしまい、未開栓であっても少しずつ蒸散して、最後には瓶が空っぽになってしまいます。
ウイスキーは保管場所以外にも、空気を触れる回数や面積で劣化に影響するのです
ウイスキーの香りや味が飛ばないようにするということであり、紫外線や酸素に出来る限り触れないようにする事が大切な事となります。
ウイスキーつまりお酒の正しい保存方法として、ウイスキーの香り分子を変質させず逃がさない事を最重要項目において書いていきます。
まず頻繁に飲む人向けの保存方法として冷暗所に保管する事です
自宅の中で最も涼しく、光の届かない場所を探して置いておくのが理想的です。
2つ目の保存方法はウイスキーの入っていた箱には、光を遮断出来るように作られる事が多いので、保管する時は箱に入れておけば、かなり良い状態で保管が出来ます。
3つ目の保存方法はパラムフィルムを使ってボトルを密封することです。
ボトルとボトルキャップとのわずかな間から、お酒なのでアルコールが抜けたり、外の空気が入ったりするのを防ぐのが、パラムフィルムです。
少し延ばしながらボトルの栓の周りに巻き付けるだけで段違いの保存環境になります。比較的長期間保存する必要があるなら、絶対に行っておきたいポイントです。
5つ目の保存方法はプライベート・プリザーブを使います
プライベート・プリザーブはもともとワイン用の商品だが、原理はシンプルです。
ウイスキーのすぐ上にガスの層を作ってしまって、酸素とウイスキーを隔離するもので、多くのワイナリーで採用されています。
最後は早く飲むことです
栓を開けてから2~3日はどれでもほぼ同じクオリティですが、1週間以上になると、徐々に変化します。出来る限り豊かな香りを愉しもうとするなら早く飲むに超したことはありません。
2015-11-04 【スタッフ豆知識】 最近人気のお酒であるブランデーの等級とはどのようなもの
ブランデーは、日本では、ビールやワインに比べれば、飲酒人口は少ないお酒かもしれません。しかしながら、ブランデーは近年、ウィスキーと並んで人気が出てきたお酒の一つです。
若い人を中心に今まではあまりお酒の中では、飲まれていなかったため、ブランデーに関する知識は、まだ一般的に広まっているとは言えません。
今回は、そのようなブランデーを選ぶ際の基準の一つとなる、ブランデーの等級について紹介します。
全国コニャック事務局で定められた基準によると、ブドウ収穫の翌年3月31日までに蒸留を終わらせる必要があり、翌4月1日から3月31日までの1年間をコントとしてカウントしていきます。
収穫年の翌4月1日はコント0としてカウントしていき、以後年ごとにコントをカウントアップしていきます。コニャックやアルマニャックのブランデーの二大産地で作られているブランデーの等級は、このコントをもとに、以下のように決められています。
コニャックでは コント2以上のものをスリースターと呼びます。コント2ですので、熟成期間は3年となります。同様に、コント4(熟成期間5年)以上を使用したものをVSOP、コント6(熟成期間7年)以上を使用したものをXO・エクストラ・ナポレオンなどと呼ばれます。
コニャックやアルマニャックの場合、これらの等級は原酒が上記の期間熟成されていなければ名乗ることは出来ないよう、全国コニャック事務局 (BNIC) や全国アルマニャック事務局 (BNIA) において厳しく規制されています。
しかしながら、コニャックやアルマニャック以外のブランデーについては、ラベル表示に関しての規制はないため、同じナポレオンと記載されていてもメーカーにより価格に大きな開きがあり、品質にも天と地ほどの差があります。ブランデーの等級は、公的な機関が定めているものではありません。製造メーカーが決めているもののため、古いから買い取り価格が高くなるとか、新しいものは安いという事にはなりません。
あくまで、一つの基準として等級という考え方があるという事です。しかし、コニャックやアルマニャックのブランデーにおいては、等級の基準が厳しく規制されているため、これらのお酒を選ぶ際には、等級も気にしてみてはどうでしょうか。
また、等級以外にもブランデーを選ぶ基準としては、産地や製造メーカー、銘柄で選ぶ事もあるため、これらを組み合わせて、ご自身が飲み易いお酒を見つけてみてください。
2015-10-16 【スタッフ豆知識】 お酒の好きな人にオススメ、美味しいブランデーの飲み方は
ブランデーはたくさんの飲み方があります。そのなかで1番オススメの飲み方はストレートです。理由は、ブランデーの香りと味をそのまま楽しむことが出来るからです。
まずは、グラスにグランデーを注ぎ、グラスを手のひらで包み込むようにして持ちます。そして、静かに回して美しい琥珀色を楽しんでください。そして、その香りを楽しんでからその味を噛み締めます。このような方法でストレートにして飲むとそのブランデーの味がよく分かるのでオススメです。特に、高価なブランデーほどストレートで飲むと良いです。
しかし、なかにはブランデーは好きだけど、ストレートは苦手という人もいます。ストレートで飲むのは少しキツいという人にオススメの飲み方は「ニコラシカ」という飲み方がオススメです。
どういう飲み方かというと、細長いリキュールグラスにブランデーを注ぎ、その上に砂糖をまぶしたレモンを乗せます。そのレモンと一緒にブランデーを飲むという方法です。この方法ならストレートでも飲みやすくなるのでストレートは苦手という人にオススメです。
そして、変わったブランデーの飲み方で1番オススメしたいのは、紅茶ブランデーという方法です。ブランデーの香りや味は好きだけど、アルコールが強くなくてお酒があまり¥飲めない人にオススメの飲み方です。やり方は、ブランデーを染み込ませた角砂糖を火につけてアルコール分を飛ばして紅茶に混ぜて飲むブランデー紅茶をティーロワイヤルと言います。
そして、おいしくブランデー紅茶を作るために1番大切なことはブランデーの分量です。火を付けてアルコール分を飛ばすので、アルコールの心配はいりません。
また、ブランデー量が多いと紅茶の味が損なわれてしまうので美味しくなくなってしまいます。ティースカップ1杯の紅茶に対してティースプーン1杯のブランデーが適量です。あとは、好みでブランデーの量を調整すると自分好みのブランデー紅茶が出来上がります。
また、紅茶に合うブランデーを選ぶのも美味しく作る秘訣になります。基本的にどのようなブランデーでも紅茶に合うのですが、ブランデーの香りが好きな人はコニャックというブランデーをオススメします。このブランデーは香り高くまろやかなのが特徴でブランデー紅茶に最もよく合います。
このように、お酒が強い人は、ブランデーをストレートで飲む方法が1番良いのですが、お酒があまり飲めない人は紅茶ブランデーという飲み方があります。どれも自分の好みで味わうことが出来るのが魅力なので、その人その人で違うブランデーを作ることができます。お酒の得意な人もお酒が苦手な人も是非ブランデーの魅力を味わって見ることをオススメします。
2015-10-16 【スタッフ豆知識】 ブランデーの種類はお酒のなかでも豊富
ブランデーは果実酒から作ったお酒のことですが、使っている果実の種類や、生産地によって様々な種類があります。
果実ですが、元はブドウを原産としてつくられていたものをブランデーと呼び、他の果実から作られたお酒と区別していましたが、今はすべてブランデーと呼ばれています。
フランス語でヴァンブリュレ「焼いたワイン」と呼ばれていたものが、オランダを経由してイギリスに持ち込まれた時に、オランダ語でブランディワイン「燃えたワイン」に変わって、ワインが取れて、ブランディと呼ばれるようになったのです。
なぜ焼いた、燃えたとついているかというと、蒸留したお酒だからなんですね。
まずこのお酒の種類は、地域によって、呼び方が異なっているものがあります。
コニャックはフランスのコニャック周辺で作られているブランデーです。15世紀ごろにはすでに生産されていたようです。品質が非常によく、高級ブランデーとして知られています。コニャックの中でも、樽による熟成の度合いによって、V.O、 V.S.O.、V.S.O.Pとわけられています。ちなみに、VはVery非常に、SはSuperior優良な、OはOld古い、PはPale透明感のある琥珀色=成熟度の高さを表しています。主な銘柄には、レミー・マルタン、カミュ、ヘネシー、マーテルなどがあります。
コニャックと肩をならべるブランデーに、アルマニャックがあります。アルマニャック地方で主に作られているブランデーですが、土の質によって、3つの産地に区分されています。
バ・アルマニャックは西部に位置し、酸性の強い粘土砂質です。フルーティーな味わいが特徴で、この産地のアルマニャックが最も高級とされています。
アルマニャック・テナレーズは中央部に位置し、粘土石灰質です。花の香りや、石灰岩由来の酸味があるとされています。
オー・アルマニャックは東部および南部に位置しており、石灰質の土壌を持ちます。中間的な性格とされています。
フランス以外で有名なブドウのお酒にピスコがあります。ペルー原産のぶどう果汁を原料とした種類で、色は透明か、琥珀色でアルコール度数は42度ほどありますが、まろやかな口当たりです。
ピスコのなかでも、ケブランタブドウから作られたPuroプーロ、香りの強いブドウであるアロマティコからつくられたAromaticoアロマティコ、発酵の過程で濾されたぶどう果汁を使ったMosto verdeモスト・ベルデ、様々な品種のぶどう果樹を使ったアチョラードなどの種類があります。
ブドウだけでも他に搾りかすが原料のマール、成熟樽をしようしない事が多いイタリア産のグラッパ、スペインのオルーホなどがありますが、ブドウ以外を主原料とするものがあります。リンゴが原料のカルヴァドス、さくらんぼが原料のキルシュヴァッサー、プラムが原料のスリヴォヴィッツ、木苺が原料のフランボワーズ、リンゴと西洋なしが原料のオープストラーなどです。
一言にブランデーといっても、これだけ種類があるので、色々試して楽しむことができますね。
2015-10-16 【スタッフ豆知識】 伝統的なお酒「ウイスキー」の文化について
今回は伝統的なお酒であるウイスキーの文化についての解説をしていきます。
ウイスキーは元々、1300年代にイタリアに留学した外交官や修道士達の手によって広められたのが始まりとされます。
このウイスキーというお酒は、やがてヨーロッパ各地に広まり、主に大麦麦芽だけを原料とするモルトウイスキーと、トウモロコシをはじめとする穀物を原料とするグレーンウイスキーの2種類に分化しました。
しかし、お酒の蒸留方法の文化や原材料の違いによっては、様々な種類に細分化する事ができ、それぞれ特色があります。
モルトウイスキーは最もメジャーな製法で作られ、単式蒸留釜で2回もしくは3回蒸留します。蒸留回数が複数である事から大量生産には向いておらず、品質を維持するのが難しいため、基本的には少数生産でお酒の販売市場に出されていきます。
また、アメリカン・ウイスキーの中でも大麦のみを原料として作られたウイスキーをシングル・モルトと呼びます。
一方、グレーンウイスキーは、トウモロコシなどの穀物=グレーンを主な原料にして、モルトにも使われる大麦麦芽を加えて糖化し、連続式蒸留機を使って作られます。
生産地の文化によって異なるものの、基本的には、原料配分をトウモロコシが8割、ピート煙臭を付けていない大麦麦芽を2割配合します。
グレーンはモルトと比較した場合、香りや味が若干乏しいのが特徴ですが、日本でも非常に多く流通しているブレンデッド・ウイスキーに溶け込ませて、強すぎる風味を和らげるものとして利用されている場合が多いです。
ちなみに、今挙げたブレンデッド・ウイスキーはモルトとグレーンの2つを配合したウイスキーです。他にも原産地の文化によって種類は様々あり、トウモロコシの原料配分を5割~8割未満に調節して配合され、
アメリカのケンタッキー州バーボンで作られているバーボン・ウイスキー。逆にお酒の香ばしい風味を楽しみたい人向けには、トウモロコシの原料配分を8割以上に調節して作られ、
バーボンと比較して熟成させなくても構わないという特徴を持つコーン・ウイスキー。テネシー州で取れるサトウカエデの炭を濾過した上で熟成して仕上げ、デネシーの伝統文化の中から誕生したデネシー・ウイスキー。原料配分にライ麦を5割以上に調節して作られ、カナディアン文化から生まれたライ・ウイスキーなどがあります。
原材料、蒸留方法や文化の違いによって多くのウイスキーがありますが、生産国ごとにもウイスキーの種類があります。
スコットランドで生産されるスコッチ・ウイスキー、アイルランドで生産されるアイリッシュ・ウイスキー、米国で生産されるアメリカン・ウイスキー、カナダで生産されるカナディアン・ウイスキー、日本で生産されるジャパニーズ・ウイスキーなどです。
ウイスキーはこのように国や文化によって数多くの種類があり、それぞれ素晴らしい特徴と風味を持っています。
2015-10-16 【スタッフ豆知識】 ブランデー原産国が作る魅惑のお酒たち
ブランデーには主にぶどうを原料として作る「グレープブランデー」と、ぶどう以外の果実を原料とする「フルーツブランデー」があります。それぞれの主な原産国はどこなのでしょうか。
まず、「グレープブランデー」の原産国としてはやはりワインの名産国が有名です。代表的なのはフランスです。すでにフランスでは14世紀頃からブランデーが作られるようになりました。
フランスには最高級ブランデー「コニャック」で知られる「コニャック地方」や「アルマニャック」を作り続けている「アルマニャック地方」などがあります。世界中の人々の憧れとなる最高級ブランデー「コニャック」「アルマニャック」の名称はアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ(AOC)と呼ばれる品質保証で厳密に規制されており、生産地、原料品種、蒸留法などが認定されなければ名称を使用することはできません。
つまり、そもそも生産地が違う他の地方で生産されたブランデーはその名称を使用することができません。AOCはフランスの食品に対する意識の高さと高級ブランデー原産国としてのプライドを感じさせます。
そのため、それ以外のフランス産ブランデーを「フレンチブランデー」と呼びます。また、フランス産以外のブランデーは一般に単に「ブランデー」と呼ばれ広く親しまれています。また、ペルーが原産国の「ピスコ」というブランデーも有名です。
ピスコは、ペルー原産のぶどうを原料としたお酒です。チリでも同様のお酒が作られていて「ピスコ」の名称が争われていますが、正式にはペルーのピスコ地方で栽培されたぶどうから伝統的な製法で製造されたものだけが「ピスコ」と呼ばれています。
ペルー最南端にある都市タクナ産のピスコはペルーでも高品質のブランデーとして有名です。
ピスコと同様の製法で作られているお酒をフランスでは「マール」、イタリアでは「グラッパ」、スペインでは「オルホ」などの名称で親しまれています。
それでは、「フルーツブランデー」の名産地はどこでしょう。すぐに思いつくのは菓子の香りづけなどにも使われるお酒「キルシュヴァッサー」で有名なドイツです。
キルシュはサクランボを発酵、蒸留したフルーツブランデーです。ドイツ・シュヴァルツヴァルト地方の名産品として愛され続けています。
以上のように、ブランデーは質と生産量ではフランスが圧倒的に群を抜いていますが、イタリア、ドイツ、スペイン、アメリカ、アルゼンチン、日本などのワインを生産している国もやはりそれぞれの土地の原料と製法でブランデーを生産しています。
世界中で作られているブランデー、その原産国ごとの個性と味わいの違いを楽しめる魅力的なお酒です。
2015-10-16 【諫早市・大村市・島原市の皆様 平和館諫早本店です】 夕焼け
諫早、長崎、大村をはじめ長崎県全域にお住まい の方こんにちは。
の方こんにちは。
金、プラチナ、ブランド品や、金券、切手ハガキ、時計、工具、絵画、
お酒、携帯、骨董品のリサイクルショップ平和館諫早本店のスタッフNです。
いつも閲覧ありがとうございます(・∀・)
本日の諫早市晴天です
秋晴れの過ごしやすい陽気です( ´艸`)
ここ数日間はお天気が良く
日中は汗ばむ陽気ですが
朝晩は冷え込んでいます
寒暖の差から体調を崩しやすくなっていますので
皆様お気を付け下さいね
昨日、近所で撮った夕焼けです

秋はいいですねヘ(゚∀゚*)ノ
リサイクルショップ平和館は、諫早市はもちろん、
長崎市、大村市、島原市、雲仙市、南島原市をはじめ、
長崎県全域のお客様のお越しをお待ちしております。
ご自宅に眠っていたり、ご不要な金、プラチナ、ブランド品、
金券、切手ハガキ、時計、工具、絵画、携帯電話、ゲーム機
などがございましたら、ぜひ一度お持ちください。
平和館諫早本店
諫早市永昌町45番4号
0957-47-9714
午前10時~午後6時 年中無休
<< 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 次へ >>